バングラデシュとは?
バングラデシュとは?
バングラデシュをご存知ですか?
1971年にパキスタンから独立したこの国は、
北海道より少し大きな土地に日本よりも多くの人が暮らしている、
国民の大半がイスラム教、
みんなカレーが大好き、
そんな国です。

チッタゴン丘陵とは?
こんにちは。
ちぇれめいえプロジェクト代表、静岡文化芸術大学の渡部清花です。
今回のプロジェクトで支援する「チッタゴン丘陵」についてお伝えします(^^)/
首都のダッカから、がたがたとバスに揺られること12時間。
まるで日本のいなかのおばあちゃんちのような山の中には
美しい自然に囲まれ、
日本人の私たちと同じような顔をした少数民族の人々が暮らしています。


仏教徒が大多数を占めますので��、お寺があったりお坊さんがいたり、

たけのこ、いも、しょうが、バナナの葉っぱ・・・朝市にはなんでもありました。

ニワトリの頭を目の前でナタで落とすのにはさすがにびっくりでした。

道を歩いていたら突然お茶に招かれ、
入ってみると大家族。
子どもたちはとにかく元気。人々はとても暖かい方たちでした。

道端で水たばこをふかす、かっこいいおばちゃん。

私は昨夏、
ここに暮らす人々と一緒に過ごし、話を聞き、現状を知ることになりました。
ここにはずっと昔から、国の大多数のベンガル人とは異なる文化や宗教をもつ先住民族が暮らしていたそうです。

こんなに美しい自然に囲まれたこのチッタゴン丘陵では1997年まで、民族紛争が20年以上続き、
人々が難民としてインドへ逃れたり、親を失ったり、大切な故郷を失ったりする中で、
子どもたちも同様に犠牲になってきました。

(現地の新聞・Daily Starより)
【チッタゴン丘陵の歴史】(ちょっと詳しいチッタゴン丘陵の歴史)
1950年代の東パキスタン時代に、政府は先住民族の権利を無視し、巨大な開発事業を行い、
1970年~80年にはバングラデシュ政府が40万人とも言われる大規模な入植政策と軍事占領を推し進め
先住民族側のゲリラ部隊と紛争へ発展しました。
殺人やレイプなどの人権侵害と虐殺事件のさなか、10万人もの先住民族が避難民となり、
12万世帯が土地を失ったと言われています。
国際社会による和解への働き掛けもあり、
1997年には政府と先住民族側の政党の間で和平協定が結ばれました。
しかし、政府は現在まで、和平協定で約束されたほとんどの項目を実施しておらず、問題の多くが未解決のまま
土地収奪や襲撃事件、レイプ事件など様々な人権侵害と民族対立が続いています。
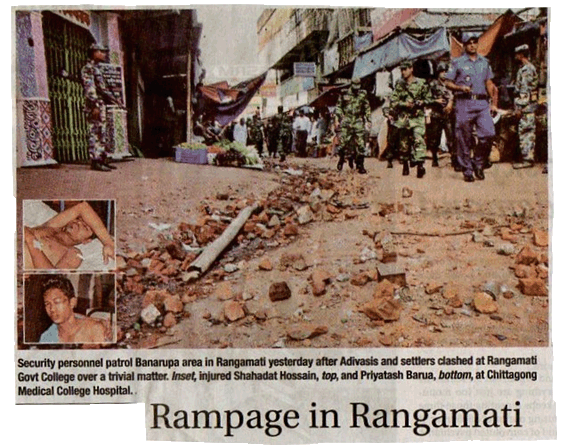
これは私が昨夏、チッタゴン丘陵を訪れたときの新聞記事です。
この日、約80人の少数民族の人々が重軽傷を負い、5人のベンガル人学生も負傷するという暴動が起きました。
美しい自然の裏にあるもう一つの側面。
「こんなの普通じゃない、はず。」 そう思いました。
民族紛争が終結した今でも、民族対立と人権侵害が人々の生活を脅かしています。
モノゴールとは?
少数民族の子どもたちのための寄宿舎学校 「Moanoghar-モノゴール-」
紛争が最も激しかった1970年代、紛争で親を失った子どもたちなどを対象にお坊さんたちが�開校した学校があります。

子どもたちが安心して遊び、学べる環境を提供しようとしている現地の寄宿舎学校です。
私は、この学校の新しい取り組みである外国語ランゲージセンターに
日本語担当ボランティア教師として1年間赴任します。
様々な手段でチッタゴン丘陵への入植政策が強行され、通学路でさえも危険と隣り合わせで、
学校に通えなくなることも少なくありません。
しかし、ここは安心して勉学に集中できる学校とあって、先住民族社会から大きな期待が寄せられています。

しかし、学校に通うにも、また維持をするにもお金がいります。
この学校に通う、またこの学校に暮らす子どもたちの中には、
両親を亡くした子どもや制服が買えない子どももいることがわかりました。
また、そもそも経済的な問題で学校に来ることさえできない子どももいるのです。
どうか、そんな子どもたちが、
当たり前に笑顔で遊び、当たり前に安心して学べる場を創りだすための
サポーターになっていただけませんか?
チッタゴン丘陵の地域づくりは、もちろん、先進国からの援助に頼るだけではできません。
そこに暮らす人々が自分たちが暮らしやすい地域を築いていくことが大切です。
そのためにこれからの地域づくりの担い手となる子どもたちを豊かに育んでいく必要があります。
だからこそ、子どもたちの遊びと学びの機会を保障したいのです。
遊びで子どもたちはたくさんのことを身に付けます。
社会性、協調性、創造性、自主性、勤勉性…。
それらを身に付けた子どもたちに学びの機会を保障することでそれぞれの持ち味がより伸びます。
そこから、自らの地域づくりに取り組む、次代を担う若者たちが育つ。
私はそう信じて、
静岡文化芸術大学の国際文化学科の仲間と共に「ちぇれめいえproject」を立ち上げました。
そこに共感してくれたデザイン学部学生も協力を申し出てくれ、
ついにプロジェクトを実行に移す段階まできました。
これで世界中の問題が解決できるわけではないけれど、
普段、光があたらない地域に暮らす私が現地で直接出逢った人々の存在を
大学生、社会人問わず、まずは多くの人に知ってもらいたかった。
そして、日本から応援している人たちがいるんだよということを
ここに生きる子どもたちに伝えたかったというのが立ち上げのきっかけです。

~地球上のどんな場所に生まれても、遊び学べる環境を~
チッタゴン丘陵の子どもたちが今日も笑顔で学校に通えるように、
彼らの未来を一緒に応援してください。

